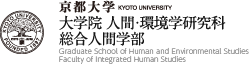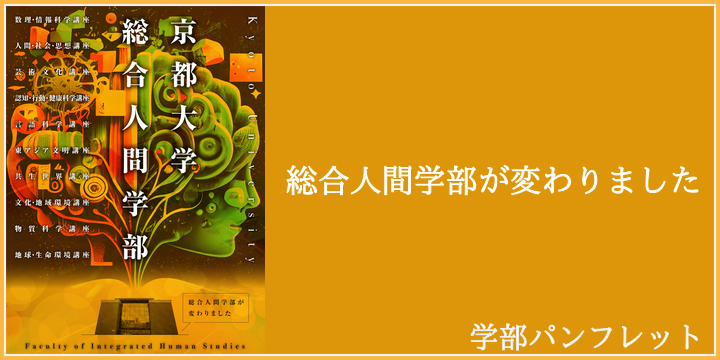- 人間・環境学研究科は、環境、自然、人間、文明、文化を対象とする幅広い学問分野の越境を通して、人間と環境のあり方についての根源的な理解を深めるとともに、近い将来だけではなく遠い未来をも見据えた先駆的研究の推進、教育研究における国際連携の強化、自然科学・人文科学・社会科学の垣根を越えた総合的な産学官連携に資する研究と教育を目指しています。
- コーディネータの指示に従い、グループディスカッション(M2院生5名のグループ+コーディネータ)の日程調整をする。
- グループディスカッションを実施する10日程度前(具体的な締切はコーディネータから指示)までに、抄録をコーディネータに提出する。
- グループディスカッションの1週間前までに発表スケジュール、発表者、責任討論者の割り当てが発表されるので、自身の発表内容を準備すると同時に、当日に自身が責任討論を担当する発表内容についての予習を行う。
- グループディスカッションにて自身の研究内容を発表する。また、責任討論者になっている発表について、積極的に質問を行う。
- グループディスカッションの報告書を作成して提出する。
上記の研究科の目的を達成するための基盤となるのが、「学術越境」する力の涵養です。「学術越境」とは、確かな専門性に軸足を置きつつ、問題解決のために分野の垣根を越えて自身の中で異分野の知見を統合して実行することと定義されています。その「学術越境」を進めるためのカリキュラムのひとつとして、修士課程の大学院生全員が参加する「教養知科目」として設定されるのが、「研究を他者と語る」になります。
「研究を他者と語る」では、専門を共有しない他者に専門学術を伝える力としての教養知の涵養を目指し、専門の異なる大学院生とお互いの研究についての議論を深めることで、狭い専門分野に閉じることなく、自身の専門知を相対化できる広い学際知を備えることを目的としています。そのため、学部生を対象とする「研究を他者に語る」よりも専門的な内容に踏み込んで議論することが求められる一方で、異分野の大学院生の間でのディスカッションを行うため、専門用語等の丁寧な解説も必要になり、それらを両立するスキルが求められます。具体的には、異なる専門分野に属する研究者との間の共同研究、異なる文化圏の研究者との対話(共同研究)、フィールド研究において関係者に自身の研究の意義を伝える状況、企業や地方公共団体等との共同研究、より専門的なポジションを目指した就職活動(特にインターンなど)などの場面、などが想定されています。
「研究を他者と語る」は、修士修了の必修科目として位置づけられており、全員の履修が必要です。大きく分けて、以下のことを実施する必要があります。