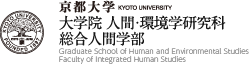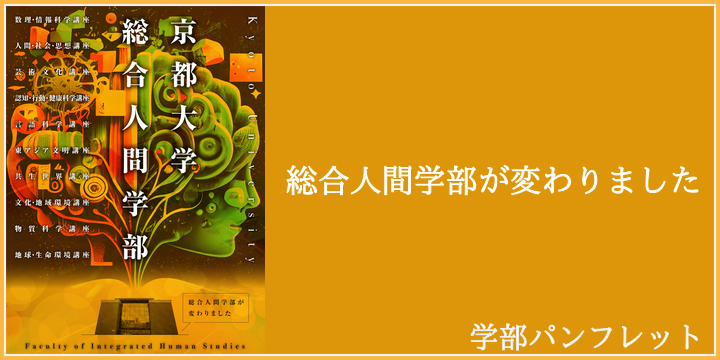大学院人間・環境学研究科は1専攻10講座で構成されています。研究科をサポートする組織として、学術越境センターが設置されています。また総合人間学部は、人間・環境学研究科に対応する形で、1学科10講座で構成されています。なお総合人間学部は平成15年度(2003年度)から令和5年度(2023年度)までは1学科5学系で構成されていました。以下では学系に関する情報も示します。
人間・環境学専攻/総合人間学科
人間・環境学研究科には人間・環境学専攻が設置され、総合人間学部には総合人間学科が設置されています。
それぞれは以下の10講座で構成されています。
| 人間・環境学専攻/総合人間学科 | |
|---|---|
| 数理・情報科学講座 | 人間・社会・思想講座 |
| 芸術文化講座 | 認知・行動・健康科学講座 |
| 言語科学講座 | 東アジア文明講座 |
| 共生世界講座 | 文化・地域環境講座 |
| 物質科学講座 | 地球・生命環境講座 |
学術越境センター
学術越境センターは、学術分野間の境界、産官学の境界、国際間の境界をそれぞれ越えた連携を実現するためのサポート組織です。学生諸君を国際交流や越境教育、就職活動等の面で強力にサポートします。
学部の構成(令和5年度以前)
平成15年度(2003年度)から令和5年度(2023年度)まで、総合人間学部は1学科5学系で構成されていました。以下では、学系に関連する情報を提供します。