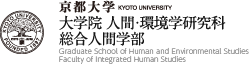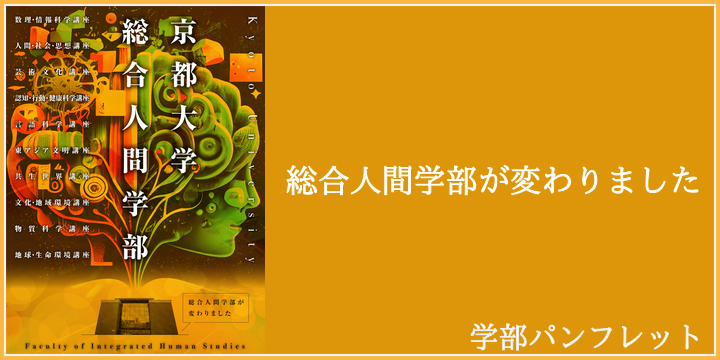馬場 基 (ばば はじめ)教授
| 研究科: 専攻等/講座 | 人間・環境学/文化・地域環境 |
|---|---|
| 学部: 講座 (学系) | |
| 所属機関/部局 | 奈良文化財研究所 |
| 電子メール | baba-h32*nich.go.jp (*→@) |
| 個人ページ | Website |

| 研究分野 | 日本古代史、木簡学 |
|---|---|
| キーワード | 古代史、都城、寺院、史料学、木簡学、文字学 |
| 研究テーマ | 大きく、3つのテーマを勉強しています 1出土文字資料を中心とした研究資源化(「情報人文学」)の挑戦 木簡などの出土文字資料は、貴重である反面多くの人にとって取っつきにくいものです。 「情報人文学」(人文情報学ではないでく、です)等を通じて、より多くの人に公開し、新しい研究を開拓することを目指しています。 2東アジア木簡の総合的研究 中国や韓国の木簡と日本古代木簡の比較研究です。 いずれも漢字の国で、制度にも共通点が多いのですが、いざ木簡をみてみるとずいぶんと様子が違います。形や書きぶり、観察や比較の視点は無限に広がります。木簡学の醍醐味が味わえる研究テーマです。 3日本古代史の研究 一応、本来の専門です。 残念ながら「このテーマの勉強をしよう」と取り組むより、仕事の必要性から勉強することの方が多いです。その結果、いろいろな課題に関わっています。 |
| 代表的著書,論文等 | 著書 『日本古代木簡論』吉川弘文館、2018。 『平城京に暮らす』吉川弘文館、2010。 編著書 『カツオの古代学』吉川弘文館、2024(共編著)。 論文 「木簡目線で万葉集を覗く」(『美夫君志』104、2022) 「日本古代漢字漢字運用規範を木簡から探す」(笹原宏之・澤崎文編『日本文学研究ジャーナルー特集 上代文献と漢字』、2022) 「門の格からみた宮の空間」(佐藤信編『史料・史跡と古代社会』吉川弘文館、2018) 「歴史的文字に関する経験知・暗黙知の蓄積と資源化の試み」(『人文科学とコンピュータ研究会報告』2017-CH-115(9)、2017) 「古代日本の動物利用」(松井章編食の文化フォーラム33『野生から家畜へ』ドメス出版、2015) 「「都市」平城京の多様性と限界」(『年報都市史研究』13、2005) 「駅と伝と伝馬の構造」(『史學雜誌』105-3、1996) など |
| 所属学会,その他の研究活動等 | 史学会、木簡学会、生き物文化誌学会 |
| 担当授業 |
|
| 経歴等 | 1995 東京大学 文学部 卒業 1998 東京大学大学院人文社会系研究科 修士課程 修了 2000 同 修士課程 中退 奈良国立文化財研究所 入所 2009 独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 主任研究員 2018 同 史料研究室長 2024 同 埋蔵文化財センター長 |